先日ちょっと話題になった話。LTE事業者が画像圧縮してるって話。
そんな話の中で、まあ、モラルの問題としてそれダメだよね、ってのに加えて、そもそも事業法の『通信の秘密』に抵触してないか、って話もあるわけですよね。
ちなみに、通信の秘密は憲法で定められた権利。事業者に限らず、他人の通信の秘密を侵してはならない、ってことになってます。
で、じゃあ『通信の秘密を侵す』ってのはどういう状態のことを言うのかな?ってのを私なりに情報を集めてみたのがこんな感じ。あらかじめ言っておきますが判例とかそういうのはまったく調べていません。あくまで総務省、つまり行政が考える法の解釈をベースにしています。
通信の秘密の侵害の三つの形はこんな感じ。
知得:積極的に通信の秘密を知ろうとする意思のもとで知得しようとする行為
窃用:発信者又は受信者の意思に反して利用すること
漏えい:他人が知り得る状態に置くこと
通信内容を見よう!という強い意志で通信内容を知ること、その内容を自分の利益などのために使うこと、他人に教えること、という感じですね。
この中で、途中で画像圧縮することは、二番目、窃用に当たりそうです。
とにかく、「発信者」か「受信者」の意思に反しちゃったら、内容を解析(デコード)した時点でアウト。解析という行為自体が「利用」ですからね。
では、件の画像圧縮が意思確認の範囲に入るかどうか。LTEユーザ、つまり「受信者」の意思確認に関しては、契約時に書いてあるからいいんじゃね、とか私はこの間書いたんですけど、どうもそこも怪しい。ってのが、やっぱり総務省のガイドラインにこんな文言があるんです。
原則として契約約款等に基づく事前の包括同意のみでは、一般的に有効な同意と解されていない
ダメみたい(笑)。で、同意を取らずに秘密を侵害してもいいケースは、正当業務、正当防衛、緊急避難に該当する場合なんですが、たとえば未成年フィルタとかマルウェア配布サイトガードとかはそういった形で未合意でもやってもいいよ、と整理されています。具体的には、それに関しては次のとおりの解釈がされています。
常時行われる対策については、一般的には、急迫性、現在の危難といった要件を必ずしも満たさないため、正当防衛、緊急避難には該当しない。
正当業務行為は、ネットワークの安定的運用に必要な措置であって、目的の正当性や行為の必要性、手段の相当性から相当と認められる行為(大量通信に対する帯域制御等)。
やっぱりダメみたい(笑)。
そうすると、端末にON/OFFを実装して『包括合意ではなく都度合意』をする必要があるんですけど、ウィルコムPHS以外はこれやってないよね(笑)。全員、アウトー(笑)。
あとね、いま、「受信者」の話ばかりしてたんですけど、「送信者」のことがまったく抜けてるんです。
受信者が意図した送信元は、もちろん、ブラウザのアドレスバーに入力したサーバアドレスなど、明確に「相手を指定」しています。そこにリクエストを送って、そこからデータをもらうってことは、「送信者」は「相手のサーバ」(の運営/コンテンツ事業者)ってことになりますよね。
同意、とってます?(笑)
世界中のすべてのウェブサーバ、データベースサーバ、その他もろもろ、インターネット経由でデータをユーザに送りうる「送信者」の合意、とってますか?(笑)。
もう、考えれば考えるほど、アウトなんですよ。なんとなく、ユーザの合意があればいいんじゃね?とか思ってたんですけど、結構アウト側走ってますよ。
たとえば、「どんなアドレスを入力しようとも、あなたの通信相手は圧縮機能を備えたプロキシサーバであり、インターネットには一切つながりません」っていうサービスとして、接続サービス(SPmodeとか)を規定してあるならセーフなんですけど、その辺どうなってますかね。たぶんそうは書いてないと思うんです。
通信の秘密とかっていう話じゃなくても、事業者諸氏は一度、送信者の意図に反して圧縮することで送信者の受信者に対するサービス品質に影響を与えちゃってる、って点については、きちんと広く説明しなきゃダメだよね、とは思うんですよ。
ということで、話題(?)の圧縮について、でした。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds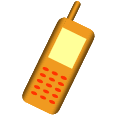 for Mobile
for Mobile