【レビュー】アプリの追加機能なし! らくらくスマートフォンは本当にスマホか? 実機に触れて”スマホ”を再考
らくらくスマートフォンは、らくらくホン(フィーチャーフォン)のいいところと、スマートフォンのいいところを見事に削りあった名機ですね。本当に、ドコモどうしちゃったんだろう、と思いましたもん。確かに、誤操作を抑える仕組みの導入はちょっと頑張ったかな、と思わないでもないんですが、だったら素直に物理キーを使ったフィーチャーフォンの形にしておけばいいのに、とか思いますよ。前にも書きましたが、ちょっと高齢とかこういうインタラクティブな操作に不慣れな人にとっては、「画面と対話する」と言うこと自体が非常に高難度なんです。決まった場所を決まった手続きで押せば決まった機能が実現できる、と言うのが「らくらく」を実現するうえで一番重要なことで、画面の状態によって同じ場所の機能がどんどん変わるというのはもってのほかだし、ある操作部と別の操作部の間に物理的なギャップがないことも操作の難度を上げます。タッチパネルは、その「操作の物理的ギャップ」をどうしても提供できないデバイスなんですよ。隣の操作部(ボタン)との物理ギャップもそうですし、押し込むことに対する物理ギャップ(ばねの抵抗力)も提供できない。バイブで「押した感覚をエミュレートする」だけじゃだめなんです。押しても一定の係数で押し返すと言う動作が必要なんですよ。ボタンから隣のボタンに指が滑りそうになっても物理ギャップで引っかかるという動作が必要なんですよ。そういった物理的な制御の力があるかないか、ってのは、普段使いする道具として非常に重要だと思うんですけどね。もちろん、ソフト的にも、Androidの制御力の弱さは目に余るし。低コストで高収益のスマホをじゃんじゃん拡販したいキャリアやメーカの気持ちもわからないでもないですが、あくまで本来の「道具としての電話機」を変わらずに提供した上での「おもちゃとしてのスマホ」の提供であるべきだと思うんですけどね。フィーチャーフォン誰も作らなくなったら、本当にどうしよう。
らくらくスマートフォンは、らくらくホン(フィーチャーフォン)のいいところと、スマートフォンのいいところを見事に削りあった名機ですね。本当に、ドコモどうしちゃったんだろう、と思いましたもん。確かに、誤操作を抑える仕組みの導入はちょっと頑張ったかな、と思わないでもないんですが、だったら素直に物理キーを使ったフィーチャーフォンの形にしておけばいいのに、とか思いますよ。前にも書きましたが、ちょっと高齢とかこういうインタラクティブな操作に不慣れな人にとっては、「画面と対話する」と言うこと自体が非常に高難度なんです。決まった場所を決まった手続きで押せば決まった機能が実現できる、と言うのが「らくらく」を実現するうえで一番重要なことで、画面の状態によって同じ場所の機能がどんどん変わるというのはもってのほかだし、ある操作部と別の操作部の間に物理的なギャップがないことも操作の難度を上げます。タッチパネルは、その「操作の物理的ギャップ」をどうしても提供できないデバイスなんですよ。隣の操作部(ボタン)との物理ギャップもそうですし、押し込むことに対する物理ギャップ(ばねの抵抗力)も提供できない。バイブで「押した感覚をエミュレートする」だけじゃだめなんです。押しても一定の係数で押し返すと言う動作が必要なんですよ。ボタンから隣のボタンに指が滑りそうになっても物理ギャップで引っかかるという動作が必要なんですよ。そういった物理的な制御の力があるかないか、ってのは、普段使いする道具として非常に重要だと思うんですけどね。もちろん、ソフト的にも、Androidの制御力の弱さは目に余るし。低コストで高収益のスマホをじゃんじゃん拡販したいキャリアやメーカの気持ちもわからないでもないですが、あくまで本来の「道具としての電話機」を変わらずに提供した上での「おもちゃとしてのスマホ」の提供であるべきだと思うんですけどね。フィーチャーフォン誰も作らなくなったら、本当にどうしよう。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds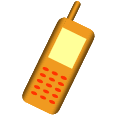 for Mobile
for Mobile
物理的な押しボタンをタッチパネル式に変えて、高齢者が困った事例が過去にあったのを思い出しました。
鉄道の自動券売機を押しボタン式から、ほとんどをタッチパネル式に変えた時に操作をできない人が多発して、大きな駅では駅員さんが操作方法の説明に飛び回っていましたね。
新聞の投書欄にも使いにくいとの高齢者からの投書があったと記憶しています。
自動券売機に、らくらくスマートフォンのような工夫はありませんでしたが、この機種のターゲット層が実機を触ったら、積極的に購入するかは怪しいと思います。