第2回人口カバー率が突いた盲点、3社3様で比較は不可能
例の人口カバー率の表示方法の統一についてのお話なんですが、あのお話にも重大な「抜け」があって、いくらでもインチキできるんですよね。ってのが、判定に使うデータの作り方については全く事業者の一存で決められる、と言うこと。実測なのかシミュレーションなのかで全然違うし、シミュレーションだと、伝播パラメータをちょいといじるだけで一気にエリアを広げられます。某事業者は伝播パラメータの一番厳しい値ではなく一番ゆるい値を使う(たとえば、受信感度について標準規定の最低保証値ではなく全端末ラインナップの中で一番実力のある端末の実力値に合わせる)などと言った方法でシミュレーション上の伝播距離を稼ぐ、なんてことをしているらしいなんて聞きますし。もうね、エリア表記とかつながりやすさとかに関しては、公平性、公正性を求めてもきりがないと私は思っています。どんな基準を作ろうが最終的には言ったもん勝ちの世界になるのが見えてますから。電波が見えない以上、どんな方法でもズルはできるわけで。いっそ、カバー率とかつながりやすさとかの表記を禁止するのが一番いいと思うんですけどね。時々公的機関で抜き打ちで何か所か毎回変わる代表地点を測定してマルバツ表でも作り、統計的にカバー率を推定する、みたいなやり方が良いと思うんですけど。手間がかかるからダメ?
例の人口カバー率の表示方法の統一についてのお話なんですが、あのお話にも重大な「抜け」があって、いくらでもインチキできるんですよね。ってのが、判定に使うデータの作り方については全く事業者の一存で決められる、と言うこと。実測なのかシミュレーションなのかで全然違うし、シミュレーションだと、伝播パラメータをちょいといじるだけで一気にエリアを広げられます。某事業者は伝播パラメータの一番厳しい値ではなく一番ゆるい値を使う(たとえば、受信感度について標準規定の最低保証値ではなく全端末ラインナップの中で一番実力のある端末の実力値に合わせる)などと言った方法でシミュレーション上の伝播距離を稼ぐ、なんてことをしているらしいなんて聞きますし。もうね、エリア表記とかつながりやすさとかに関しては、公平性、公正性を求めてもきりがないと私は思っています。どんな基準を作ろうが最終的には言ったもん勝ちの世界になるのが見えてますから。電波が見えない以上、どんな方法でもズルはできるわけで。いっそ、カバー率とかつながりやすさとかの表記を禁止するのが一番いいと思うんですけどね。時々公的機関で抜き打ちで何か所か毎回変わる代表地点を測定してマルバツ表でも作り、統計的にカバー率を推定する、みたいなやり方が良いと思うんですけど。手間がかかるからダメ?
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds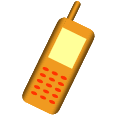 for Mobile
for Mobile
[…] 引用元: ニュースコメント[2013-07-09] | 無線にゃん. […]