フレッツ 光でのIPv6インターネット普及に向け“ネイティブ枠”拡大など
googleに名指しでインチキv6呼ばわりされたNTT東西が、ホンモノv6の拡大に本腰を上げそうな雰囲気ですが、そもそものフレッツ網内用v6アドレスなんていうインチキくさいものを使っていること自体をどうにかすべきですね。そもそもv6になれば同じv6体系で閉域網も共存できるようなコンフィグがあるはずなのに、おそらく、「世の中v6なんてまだまだだし、とはいえフレッツユーザを全収容するにはv4プライベートでは心配だから、テキトーにv6使って一意割り当てしちゃおうぜ」なんていう先を全く見ない考え方でインチキv6をフレッツ網内アクセス用に使ってしまったんじゃないか、って感じです。相変わらず、としか言いようがないですが、NTT系は、伝送系はキチガイじみた技術を持っているのに、上位層(IP以上)に関しての見識は、本当に低いですね。そういえばうちのauひかりはv6らしいんだけど、KDDI系が世界有数のv6接続なんですね。まぁ、全ユーザいつの間にか勝手にv6アクセスになってるわけで、数でいえば確かにそうなのかもなぁ、なんて思ったり。今のところ、我が家では特に不都合にぶつかったことはないです。まぁそんなことで不都合が生じてちゃぁダメなんでしょうけど、相当混乱するだろうなーと思ってたv4/v6遷移期が意外とすんなりと行きそうで、ちょっとがっかり(えぇ~)。
googleに名指しでインチキv6呼ばわりされたNTT東西が、ホンモノv6の拡大に本腰を上げそうな雰囲気ですが、そもそものフレッツ網内用v6アドレスなんていうインチキくさいものを使っていること自体をどうにかすべきですね。そもそもv6になれば同じv6体系で閉域網も共存できるようなコンフィグがあるはずなのに、おそらく、「世の中v6なんてまだまだだし、とはいえフレッツユーザを全収容するにはv4プライベートでは心配だから、テキトーにv6使って一意割り当てしちゃおうぜ」なんていう先を全く見ない考え方でインチキv6をフレッツ網内アクセス用に使ってしまったんじゃないか、って感じです。相変わらず、としか言いようがないですが、NTT系は、伝送系はキチガイじみた技術を持っているのに、上位層(IP以上)に関しての見識は、本当に低いですね。そういえばうちのauひかりはv6らしいんだけど、KDDI系が世界有数のv6接続なんですね。まぁ、全ユーザいつの間にか勝手にv6アクセスになってるわけで、数でいえば確かにそうなのかもなぁ、なんて思ったり。今のところ、我が家では特に不都合にぶつかったことはないです。まぁそんなことで不都合が生じてちゃぁダメなんでしょうけど、相当混乱するだろうなーと思ってたv4/v6遷移期が意外とすんなりと行きそうで、ちょっとがっかり(えぇ~)。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds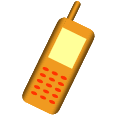 for Mobile
for Mobile
> そもそもv6になれば同じv6体系で閉域網も共存できるようなコンフィグがあるはずなのに
そういう問題ではございませんで、NTT法と政治的問題と技術的問題の複合的問題なのです。
NGN の IPv6 アドレスで外にでることは技術的にはもちろん可能です。
しかし、現行のNTT法2条3項1号の「地域電気通信業務」のところでNTTは県外接続を禁止されているため、
NTTはISP業を行うことができません。
ので、NTTがISP業を代行という形にする案も当初はあったのですが、これについてはISPのネットワークを
一切経由しなくなるため、ISPが反発し、没になりました。
この案がなくなった時点で、NGNのIPv6アドレスでそのまま外には出れないことが確定しています。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090805/335170/
その後、ISPのIPv6アドレスをNGN内で使えるようにするという案4が出され、これが採用されました。
各社のIPv6アドレスが混在するとルーティングが大変になるのですが、これはNTTが頑張る…けど3社が当時は限界でした。
で、処理性能が上がったため多少緩和するというのが今回の話です。
現在の状況は「NTT東西のIPv6サービスが2方式あるわけ」が比較的まとまっています。
http://ascii.jp/elem/000/000/647/647620/
> naruseさん
あー、なるほど。法的な問題を完全に失念していました。確かに、グローバルで使えるv6をNTT東西自身が割り当てちゃうと、県間通信に抵触しちゃいますね。
しかしそれであれば、ちゃんとルータ(ONU)に細工してフレッツ網内v6が宅内ローカルに漏れ出ないような仕組みにもできたとは思うんですけどねぇ。やっぱり何となく、「どうせv6なんて当分誰も使わないから」みたいなやっつけ感を感じないではないのです。
> しかしそれであれば、ちゃんとルータ(ONU)に細工してフレッツ網内v6が宅内ローカルに漏れ出ないような仕組みにもできたとは思うんですけどねぇ。
それはトンネル方式のことです。
上記に出している「2種類」のもう一方ですね。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110526_448603.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090805/335008/
> やっぱり何となく、「どうせv6なんて当分誰も使わないから」みたいなやっつけ感を感じないではないのです。
同じ感想自体は抱いているのですが、この問題はNTT方を筆頭に、複数の関係者の利害や歴史的経緯とコスト問題など、
なかなかに複雑な問題なので何か言う時はよく調べた方がいいんじゃないかと思います。
たぶん、よく調べると出てくる、インターネットユーザを第一に考えた結論は、
「NTTのばーか」どころではない過激な結論になるんじゃないかと。
そもそも論で言わせていただければ……。
閉域網内で接続するためだけのアドレスに global unicast addressを使っていることそのものがよろしくないと考えますです。IPv6には、ちゃんとそういう用途のために site local address とか unique local address とかそういったアドレスがあるのに、なんで使っていないのか、よくわかりません。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/rensai/v6again01/01.html
まぁ、わたしは今のところFlets使っていないので関係ないですが(笑)
FLETSは昔閉域網内でv4プライベートアドレスを使って痛い目にあってますから、v6で確実にユニークなアドレスを使うというのはわかります。
しかし、今の実装はユーザから見たらクソ以外の何物でもない。法律の規制なんぞ最初からわかっている事だし、ISPとの接続についてもどう転ぶかわからん状況であの実装は考えがなさすぎだろうとしか。
その後、IPv6 over PPPoE接続のNATネタは目が点になりましたし。
うちはFLETS NEXTですが、FLETS側のIPv6はルータで全部捨ててOCNのv6のみを使っています。FLETS内のコンテンツは見る気などないので全く困っていません。:)
>miさん
SLA/ULAは、「マルチプレフィクス問題」を解決するには有効ですが、今回 Google が怒っている「v4/v6フォールバックで時間がかかる問題」を解決することはできません。この二つは、よく混同されがちなのですが、別物です。
SLAはRFC 3879でdeprecatedになってるので、ないと思います。
ULAも広域での使用が禁止されているので、NGNでの用途には使えません。
ローカル専用のIPv6アドレスがあれば解決できるんじゃないかというのは正しいと思うんですが、
そもそも広域な閉域網ってものの存在自体がIPv6と相容れない感が。
まぁ、わたしもIIJでIPv6トンネルしちゃってるので完全に他人事ですけど。