本日はauとUQをまとめて考えます。いや、まとめて考えてあげないとかわいそうなくらい悲惨な状況(笑)なので。
au、つまりKDDIは、日本で唯一の市内インフラ+県間インフラ+国際インフラ+衛星インフラ+CATVインフラ+移動体インフラを一社で手がける企業です。・・・のはずです。実際にはばらばら。唯一の接点は請求書。別会社体制のソフトバンクグループよりばらばらのサービスです。
そんななかで、結局auは、独立した携帯電話会社として巨人ドコモやソフトバンク軍団と戦おうとしている。これじゃぁ勝てるわけがありません。UQとの連携サービスもようやく1個だけ始まりましたが、焼け石に水。au+UQの純増数で2位のドコモに及ばず、3位のイーモバイルを何とかしのげたか、と言う程度です。笑えるほど弱い。
これがどうしてこういうことになっているのか、と言うことを考えるにつけ、やはりどうしても気になるのが、auの戦力の「質」。端末・サービスの「種類方向」の戦略です。
はっきり言うと、auの戦略はきわめて単純で、「ドコモに対して、対称戦力をぶつける」と言うもの。対称、つまり、鏡に映したようにそっくりそのままの戦力を正面からぶつけるということです。2001年ごろはこの関係が逆でしたが、2003~4年ごろにサービス先行マージンがなくなりドコモに追い抜かれた頃から、auがドコモの対称戦力で後から追う方向で進んできています。
一方、ソフトバンクは、ドコモに対して「非対称戦力」で戦っています。ドコモにないもの、ドコモサービスと競合しないもの、共存共栄できうるもの、と言う観点です。別の言い方をすれば「ドコモとソフトバンクは直交している」ともいえます。auとソフトバンクの戦略の決定的な差はここにあると考えます。
対称戦力での対抗、つまり正面作戦は、確実に「量」で勝負が決まります。物量に勝るほうが勝つ、と言う原則に従うわけです。とすれば、ドコモにauが物量で勝っているかと言うと、これはもうまったくかなうはずもありません。auと固定を含んだKDDI全社でさえNTTの移動部門会社に過ぎないドコモ1社にはるかに及ばない戦力量です。これはもう勝てるわけがありません。
一方、ソフトバンクはドコモと直交したサービスや端末でシェアを伸ばしています。これは実は、ドコモにとってはまったく脅威ではありません。ドコモは淡々と王道のサービスを提供すればよいのです。現に、ドコモの純増数はソフトバンクの台頭によってもほとんど揺らいでいません。
ところが、ドコモが対ソフトバンク戦略として物量供給を増やした結果、それに正面からぶつかっているauが最大の被害を受けてしまう結果となってしまっています。むしろ、非対称戦力で戦っているソフトバンクはまったく影響を受けていません。auは完全にとばっちりといわざるを得ません。
しかし、ここにauの戦略のまずさがあります。そもそも量で勝てない相手に正面作戦を挑んだことが間違いであり、ドコモが直交競合に対して物量で攻める兆候を見せたときにすぐに別の直交軸に逃げ出さなかったことが大きな間違いです。
どんな市場であれ、飽和した市場においては、軸を共有する競合同士は必ずどちらかが相手を滅ぼすまで競争が続きます。ソフトバンクはそこからいち早く抜け出し、直交軸での共存を図りました。であれば、auも直交したサービスや端末を目指さなければなりません。そもそも、WCDMAとCDMA2000と言う違う技術であり直交化がソフトバンクが行うよりも容易であったはずなのに、それをまったくしなかったことが、auの敗因です。
市場での共存を考えるときは、先に新しい軸を作ったほうが有利です。auが今からソフトバンクの軸に算入しても勝ち目はありません(いまさらスマートフォンに力を入れるなんて愚策の極みです)。となると、ドコモとも直交しソフトバンクとも直交する新しい軸を作らなければなりません。これは、ソフトバンクがドコモと直交する軸を作ったよりもはるかに難しい試みとなるでしょう。
UQや固定(光・ケーブル)との連携が、この軸を作る一つのヒントと成りうるかもしれません。固定との連携はドコモは法的にできないしソフトバンクは「実質的に持っていない」と言う、KDDIだけの特徴。単なる大幅なセット割引(いっそ光かケーブルを持ってたらauはパケット定額まで含めて無料、くらい)あたりが、唯一戦える戦場になるのではないでしょうか。
とにかく、ドコモとの共存戦略を誤りガチンコバトルとなった末の今の窮状ですから、まずはそこから逃げ出すのが、auの今後の急務といえそうです。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds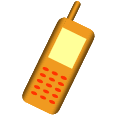 for Mobile
for Mobile
ddiポケットをデータ重視にしていた時が思い出されます。あの流れが続いていたらどうなってたんだろぅ。