奄美大島で被害にあった皆様には心よりお見舞い申し上げます。おそらくまだ現在進行形であろう奄美大島での豪雨被害ですが、被害拡大に拍車をかけているのが、通信手段の途絶と言われています。
特定の地域内では携帯電話は停電のために軒並み停止、固定電話も回線が寸断されている状況とのことで、こうなってしまうと連絡手段がありません。
しかし、タイトルにも書いてありますが、こういうときのために衛星携帯電話があります。ところが、この衛星電話も配備数・配備率が足りなかった模様で、必要な災害対策拠点にないという状態だそうです。
業界的な話になりますが、業界では衛星携帯電話を「既に終わった技術だ」と見ている人と、「これからは衛星だ」と見ている人と、極端に二分されています。そして日本では、圧倒的に前者が多い模様です。
そのため、日本の事業者は衛星電話サービスの拡充にも消極的で、今飛んでいる衛星が落ちたらやめちゃおう、くらいに考えている、と聞いています。
ところが、海外、特にアメリカでは、「衛星はこれからの技術だ」と考えている人や会社が多いようです。多くの会社が衛星携帯電話の技術開発に積極的で、最大手のAT&Tも新たにGSMベースの衛星電話サービスを開始しましたし、二位のVerizonもCDMA2000の衛星版を開発中です。
固定電話は銅線や光ファイバなどの「線」でつなげるもの、と言うことに対して言えば、携帯電話はその大部分を無線に変えたという意味で全く違うサービスです。
しかし、衛星電話は、携帯電話で必要だった「基地局までの線」さえ不要としてしまった、これまた全く新しいカテゴリのサービスです。「地上線」に依存しないサービスとしてはおそらく唯一のシステムです。
つまり、衛星電話は、他の固定や携帯では実現できないサービス性を提供できます。一つは、今回のような災害時に全く影響を受けない、と言うサービスの持続性(コンティニュイティ)です。
いわゆる「ビジネスコンティニュイティ」を考えるとき、固定や携帯はやはり実際に今回のように全滅する可能性はあります。となると、衛星が頼りですし、そういうことに備えて衛星を積極的に利用すべきです。
たとえばイリジウムは、複数の地上局と衛星間のメッシュネットワークで、地上局が災害にあったり衛星が一つ二つ潰れてもサービスは継続されます。それでいて月額5000円で維持できるわけですから、これはきわめてコストパフォーマンスが良いと言えます。
他の静止衛星を使ったタイプのシステムもイリジウムほどではありませんが、災害にはきわめて強い特性を発揮します。たとえば、日本をカバーする衛星電話で地上局は韓国などに置く、と言う方法で地上網+衛星で冗長化ができます。
もっと衛星を見直すべきだと私は思うのですが、なかなか日本ではイリジウム倒産のイメージが根強くて「終わったネタ」としかとらえられていません。私は近い将来かなり大きなビジネスチャンスが来るんじゃないか、なんて思っていますが、さて、イリジウムファンドでも立ち上げてイリジウムのオーナーにでもなろうかなぁ(やりすぎ)。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds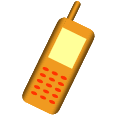 for Mobile
for Mobile