セブン-イレブン 23区1200店に非常用電話と言うニュースに関して、災害時に繋がりにくくならない回線ってなんなんでしょう、と言う趣旨のご質問をいただきましたので、簡単に。
えー、ざっくりと言ってしまうと、基本的には、日本の通信事業者は法令に従って「災害時優先電話」の仕組みをみんな備えています。なので、災害時に繋がりにくくならない電話としては、どの事業者の回線を使っても同じです。
もちろんNTT東西も優先電話システムを持っていますので、その回線をセブンイレブンに引っ張って配備すればOK。これで疑問は解決ですね。よかったよかった。
・・・と言いたいところですが、法令ではもう一つ決まりがあって、それは、「優先電話が置けるのは法令で定められた対象だけ」となっています。それは、救急・消防、警察、自衛隊、ライフラインインフラ事業者、新聞・通信・放送事業者、その他の防災機関、と言う感じになっています。どう考えてもセブンイレブンはこれに該当しません。
それはそうで、元々法令で優先電話を決めたのは、こういった機関の通信を確保したいからで、こういった機関以外にも無節操に優先電話をばら撒いていては、そもそもの「優先したい」と言う目的を達成できなくなります。優先電話同士で輻輳が起きてしまうからです。
さてこういった縛りがある中で、どうやってセブンイレブンへの災害用電話配備を成し遂げたのか。私は、二つの方法のどちらかだと思っています。
一つ目は、NTT東日本の独断で、セブンイレブンの1500店舗を「その他の防災機関」に指定した、と言うもの。対象の指定は、実は事業者の判断に委ねられています。もちろんあんまり外れたことをやると怒られるんでしょうが、災害時の通信用スポット、と言う考え方であれば、それがたまたまセブンイレブンでした、と言い張ることはさほどおかしいこととは思えません。
もう一つは、公衆電話。実は、公衆電話は、優先電話に指定されています。それは、災害時などの通信用スポットとして機能させるため。また、公衆電話自体は事業者自身の持ち物なので、「優先電話を該当しない団体に与えた」と言うことになりません。であれば、そういった「公衆電話」がたまたまセブンイレブン1500店舗にくまなく配備されているんです、と言う言い分でこのサービスを実現することが出来ます。
と言うことで、上記のどちらかで実現しているんだろーなー、とは思うのですが、ここから先はよく分かりません。多分後者かなぁ、と言うくらい。と言うことで、災害用電話のコンビニ設置のからくりについての考察でした。でわ。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds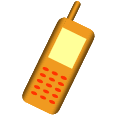 for Mobile
for Mobile
初めまして。
携帯が普及する以前のコンビニには
必ず公衆電話(グレor緑)がありましたねぇ。
で、公衆電話そのものは撤去してしまっても
ラインは引いたままだったのでそれを生かしたのかな、なんて。
あ、でも携帯普及後の新設店舗(=最初から公衆電話なしで作られた店)だと話が合わないか・・・。
普通に自治体との防災協定根拠で優先引いたんでしょ。
コンビニは大抵、自治体と帰宅困難者支援の防災協定結んでるから。