本日はOFDMの話。面倒だけど。
まず、OFDMの基礎技術、「FDM」について。このFDMは、以前アクセス方式で軽く説明しましたが、無線通信ではもっとも古い多重化技術です。FはFrequencyのF。つまり、周波数です。周波数方向で多重する技術です。周波数というのは、電波の振動の速さ。この振動の速さを変えることで、異なる信号を送ることができるわけです。一番単純には、テレビやラジオ。テレビやラジオの「チャンネル」とか、そのものずばり「周波数」ってのと全く同じです。
テレビよりもラジオの例の方がわかりやすいと思うのですが、ラジオの周波数って、特に最近のデジタルな表示だとわかるんですが、とびとびにしか変わりません。例えば、1008kHzの次は1017kHzと言うように決まっています。これは、ある周波数にデータを乗せると、その周波数を中心にしてその周囲に周波数成分が広がってしまうからです。つまり、1008kHzの放送は、1003.5kHzから1011.5kHzまでをぼんやりと広く占有してしまいます。
と言うのがFDMです。つまりFDMのキモは、「周波数によって他の通信と区別する」「ある幅を占有してしまうため隣との間に一定幅が必ず必要」と言うこと。
で、この「占有してしまう幅」ってのは、話を単純にすれば「データ通信速度」に比例します。速度を速くすればするほど占有幅は広がってしまうわけです。だから、通信速度がどんどん速くなる昨今では、FDM単体ではとてもでは無いけれども周波数が足りないわけで、TDMやCDMとの併用が最低限となっています。
そう、FDMは、もっとも古い技術でありつつも、今でもあらゆる通信方式で他の方式と併用されている、と言う点がポイントです。他の方式はいろいろと改良されてもはやこれ以上の改良は難しいと言う所まで来ています。むしろ、元から改良の余地のない程効率の高い方法ばかりなのです。そこで、ついにFDMにメスを入れることになります。
FDMで分割した通信同士は、異なる周波数でそれぞれに幅を持っています。以前の椅子の例え話で言えば、一人に一脚の椅子があり、その椅子は一つ一つが決まった幅があって、整然と並んでいる、そう言うイメージです。その椅子の、一脚につき一人が座ると言うのがFDMの基本です。
それでは、OFDMは一体なんなのか、と言う話。手っ取り早く椅子の例で話しますと、例えば10脚あった椅子に10人が座っていたとします。ここで、10脚の椅子を取っ払って、同じ長さの長いすを置きます。電車の長いすみたいなイメージですね。ではここに10人座りましょう。これでは何も変わりませんね。
ここで、この10人を入れ替えて、ものすごく仲のいい20人を連れてきます。仲のいい人同士なので、ぴったりとくっつきあって座っても不快じゃないですよね。いや、不快じゃないということにしといてください。そんなわけで、端っこからぎゅうぎゅうに詰めて、長いすに20人座れるようになりました。となりますと、同じ長さの椅子だったのに、個別の椅子だったのを長いすに変えただけで倍の人が座れたわけです。こうやって効率を上げるのが、OFDMです。
ポイントは、「仲のいい人」って所。細かい話は省きますが、ある人と隣の人、普通は「お尻の幅くらい」は離しておかないと混信してしまうのですが、隣ともっとくっつけても、と言うよりむしろ半分重なってしまっても、隣と混信しないと言う「仲のいい組み合わせ」があるんです。これを数学用語で「直交する」と言います。OFDMのOは、Orthogonal(直交)のOです。半分重なるって幽霊かお化けの世界ですが、とりあえず細かいところはここではとばして、とにかくそう言う関係が存在する、ってことです。
そうやって、隣との幅を極限まで詰め込んでしまえば、これまでよりも飛躍的にたくさんのチャンネルを作ることができます。そこで、通信する端末同士が、いくつもの(と言っても5個や10個ではなく、100とか200とか言う単位です)周波数を一気に束ねて使うようにすれば、それぞれのチャンネルを別個の人が使うよりも非常に効率よく使えるようになります。と言うわけで、OFDMは、多重化技術としてよりも、効率化・高速化技術として注目されているわけです。
最後にOFDMの応用例ですが、まず最初に一般向けに実用化したのは、無線LAN。近距離で1対1で通信し、消費電力の制約も比較的緩いため、割と早い時期に実現しました。と言えばわかるかと思いますが、遠距離で多対多で消費電力の制約も厳しいと言う状況では、まだOFDMは使いにくいと言うことです。で、無線LANの次に実用化したのが、いわゆる固定WiMax。次いでモバイルWiMaxがそろそろ実用化という所に来ているようです。また、商用化が始まったLTEもOFDM。その他、新しい通信は多かれ少なかれ、OFDMを使った「超高効率化」を必ず取り入れています。
という感じで、OFDMについて書いてみました。もう少し技術よりのお話はまた稿を改めさせていただくこととして、今回はこれにて。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds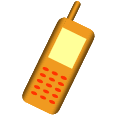 for Mobile
for Mobile
[…] This post was mentioned on Twitter by kou molu, 無線にゃん. 無線にゃん said: OFDM http://wnyan.jp/117 […]
[…] OFDMに関しては大雑把な説明をこちらに置いてありますが、一つの周波数を細かいサブキャリアに分けて使う方式。なので、それぞれのサブキャリアの中の一つのシンボルが最小単位になります。WiMAXでは、この最小単位を碁盤の目のように並べたグリッドを想定し、その平面の中から長方形に切り取った区画ごとにユーザに割り当てます。 […]
[…] 概念的な説明に終始したOFDMの技術解説、今回は、FAQ形式でOFDMの技術について解説してみたいと思います。 […]