さて先日のインフラ力分析を受けて、「インフラ最強のドコモとはいうけど、実際に使っていると印象が違うがどういうことだろうか」と言うメールをいただきました。
具体的には、レスポンス。RTT。要するに、インターネット接続をして使っているときの、そのレスポンスの速さで言うと、ドコモはいまいちだというお話です。
実は私もそれは認識しています。ちょっと古いデータですが、全社のpingデータを取った2年ほど前の記録によると、ドコモが120ms台、auがもう少し遅くて180近く、ソフトバンクがさらにやや遅くて200ms台、イーモバイルは90ms前後くらい、ウィルコムが6、70ms程度、と言う結果が出ています。詳しくはレスポンスを比べてみるをご覧下さい。
実のところ、インフラの強さとユーザエクスペリエンスはそのまま比例はしません。インフラの強さ弱さよりも、無線方式、ネットワークアーキテクチャ、そして何より事業者ポリシーによるところが大きいからです。たとえば、あるノードのポリシーについて、「輻輳を起こし易くなっても良いからレスポンスを最優先する」と言う設定もできるし、「輻輳を出来るだけ防ぎそのためにレスポンスを犠牲にする」と言う設定も出来ます。輻輳だけでなく、バルクのスループットだったり収容セッション数だったり、レスポンスのトレードオフになる要素は山ほどあります。
上のリンク記事の中にも軽く書いてありますが、たとえばドコモとauのレスポンスの差は、ほぼ100%、方式による差であると特定できます。一方、同じ方式のドコモとイーモバイルの差、これについては、ネットワークアーキテクチャとポリシーの差です。
ドコモは、イーモバイルに比べると圧倒的に多数の加入者を抱え、パケット接続トランザクション数で言えば100倍では足りないでしょう(iモードによるこまめな接続・切断が繰り返されるため)。くわえて、IP接続契約者数から推定すれば音声ユーザは1000倍の規模に近いはずです。
携帯電話サービスでは、パケットよりも音声を優先するのが基本です。少なくともWCDMAでは音声もパケットも全く同じ無線帯域を共有するので、音声が多ければその分パケットを我慢しなければなりません。我慢するにも単に割当を小さくする方法もありますし、あるいは、できるだけ無線ペイロードぎりぎりの大きさにまでデータを貯めてから送信することでパケット占有率を下げるとう方法もあります。つまりパケットを最適化する過程で「待つ」と言う動作をあえて入れているためにレスポンスが落ちるということはありうるんですね。
こういった原因でのレスポンスの低下はもちろん一例に過ぎませんが、ネットワークにどの程度余裕を持たせるか、パケット通信のためにどの程度処理能力や有線/無線リソースを無駄づかいしても良いのか、そういった事業者ポリシーにより、レスポンスを調整しているという面があるわけです。
そういった中で、たとえばUQやイーモバイルなどの(実質)データ専業事業者では、データに特化することで数々の頚木を逃れ、思い切ったレスポンス向上の設定をすることが出来る、と言うことができます。
と言うことで、質問者の方も、WiMAXやイーモバはかなりレスポンスが短いけどドコモはどうしようもなく遅い、と書かれていましたが、莫大な音声加入者数を持つ以上、データ専業事業者に対してデータの性能で上回るのはさすがに難しい、と言えます。
もちろん、こういった理由も無く、本当に単なるインフラの弱さのためにレスポンスやセルスループットを落としてしまうようなことも起こりうるわけです。ただ、もし「インフラの弱さ」がレスポンスの低下を起こしているのなら、その場合は時間によってそれが大きく変動します。レスポンスでいうなら、極端に言えばレスポンス時間が有限の値から∞(レスポンスが返ってこない=パケットロス)の間でふらつくような状況(要するにランダムなパケロス)というのは確実にインフラの弱さです。逆に、レスポンスが多少遅くても時間帯に寄らず一定しているのなら、そのインフラはきわめて強いと言えます。インフラの強さを測るには、絶対値よりもその揺らぎの大きさを見るべき、と言うことです(もちろん、サービス利用者としては要件として絶対値を見るのが当然ですが)。
取り留めなくなりましたが、要するに、技術もポリシーも違う中ではさまざまな性能の絶対値自体はさほどインフラの強さを反映せず、むしろその与えられた絶対値がどれだけ安定しているかと言う方がインフラの強さを反映するのです、と言うことが言いたかったわけで。100Mbps出ます!と謳うサービスの実効速度が日によって10Mだったり90Mだったりするよりは、1Mbps出ます!と言うサービスが毎日変わらず1Mbpsで安定しているほうが「インフラの力がある」と言える、と私は考えます(自身のNWの実力を正確に把握できているという意味でも)。
もちろんベストエフォートのパケット通信で、サービスレベルの補償をしている例はまず無いと思いますが、最大瞬間風速よりもいかに必要な時間・必要な場所で必要な性能を安定して得られるかを重視する、と言う選び方もあります。最大瞬間風速をたたき出すのは比較的簡単ですが、安定した性能を出すことは非常に難しい、そこがインフラの底力として見えてくるわけです。そういった強さがありそれが評価されたからこそ、ミッションクリティカルな用途、たとえばIC決済自販機やタバコ自販機のTaspo対応などで、ドコモが選ばれる、と言うような結果となって見えてくるわけです。
と言うことで、インフラが強いはずのドコモなのにレスポンスがよろしくないのはなぜ、というところについて簡単に自説展開のひとことでした。でわ。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds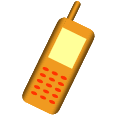 for Mobile
for Mobile