当分はコストダウンより機能競争を進める…ソフトバンク孫社長
コストダウンよりも競争を優先する、もう少し翻訳すれば、戦略的にコストを増して(仮に利益を削ってでも)競争力をつける、ということです。こういうことをリーダーシップをとってできることが、孫先生のすごいところです。ドコモやKDDIでは、コストを大幅に増すような施策を提案したとたんに社内の抵抗勢力が一斉に袋叩きにする風潮があるようで、結局は、コストを増やさない範囲での穏やかで保守的な施策しか打てなくなっているようですね。なんで数千億の利益のある会社があんなに保守的なのか、不思議なくらいですよ。ドコモ(というかNTT)でもKDDIでも、不振のウィルコムを二束三文で買って帯域やシステムやロケーションや顧客基盤を活用すればいいのに、という話はあったらしいんですが、結局はその二束三文の「コスト」さえ目の敵にされて消えて行った、なんていう噂話も聞こえてきます。結果を見れば、本当に二束三文でウィルコムを買ったソフトバンクがTD-LTE 110Mbpsというトップスペックを広告に載せられるようになっていますよね。コストに対して即リターンを求めず、先の先を見たコストのかけ方をする、教科書レベルの当たり前のことだと思うんですが、当たり前のことを当たり前に実行していく意志の強さ、リーダーシップ、それが孫先生の強さだと思います。いや、5年もしないうちに、ドコモもKDDIもソフトバンクに追い落とされるんじゃないかな、ほんと。
コストダウンよりも競争を優先する、もう少し翻訳すれば、戦略的にコストを増して(仮に利益を削ってでも)競争力をつける、ということです。こういうことをリーダーシップをとってできることが、孫先生のすごいところです。ドコモやKDDIでは、コストを大幅に増すような施策を提案したとたんに社内の抵抗勢力が一斉に袋叩きにする風潮があるようで、結局は、コストを増やさない範囲での穏やかで保守的な施策しか打てなくなっているようですね。なんで数千億の利益のある会社があんなに保守的なのか、不思議なくらいですよ。ドコモ(というかNTT)でもKDDIでも、不振のウィルコムを二束三文で買って帯域やシステムやロケーションや顧客基盤を活用すればいいのに、という話はあったらしいんですが、結局はその二束三文の「コスト」さえ目の敵にされて消えて行った、なんていう噂話も聞こえてきます。結果を見れば、本当に二束三文でウィルコムを買ったソフトバンクがTD-LTE 110Mbpsというトップスペックを広告に載せられるようになっていますよね。コストに対して即リターンを求めず、先の先を見たコストのかけ方をする、教科書レベルの当たり前のことだと思うんですが、当たり前のことを当たり前に実行していく意志の強さ、リーダーシップ、それが孫先生の強さだと思います。いや、5年もしないうちに、ドコモもKDDIもソフトバンクに追い落とされるんじゃないかな、ほんと。
【ワイヤレスジャパン2012】
ドコモ山田社長が中期経営ビジョン解説
ネットワーク上に機能を埋め込んで行って端末をシンクライアント化していくというコンセプトを語り、これをもって「単なる土管化を防ぎたい」と言っているわけですが、私はこれは時期尚早、というか、それを前提としたサービスを基本に据えることは根本的に間違ってるだろ、と思わざるを得ません。言っちゃぁなんだけど、他のキャリアも含めて、「単なる土管」にさえなれてないよね、実際。地下鉄トンネル内は相変わらず圏外だし都市部では網の輻輳でパケットが通らなくなることなんて日常茶飯事。当然、エリア化されていない地域もまだまだ多く、ちょっとしたお出かけでも圏外に当たることはいくらでもあります。何より(高額な料金を払わない限り)海外は圏外だよね。ということを本当に自覚してないんですよ、この発言は。通信が電波や線に頼ったサービスである限り、それが届かない場所は必ず残るんです。どんなに頑張っても。なのに、「通信が疎通していることを前提としたサービスを基礎的サービスとして位置付けていく」というのは、おこがましいにもほどがある。不遜ともいう。ネットワークの提供は頑張るけど、それでも届かない人のためにもいろんな仕組みを用意してあげようというのが、土管化を防ぐために必要なことじゃないかなぁ、と思うんです。そのために、端末などのエンドノードにいろんな仕掛けをしてあげて(もちろん対向の提供側向けにも仕掛けは必要)、仮にネットワーク(=土管)に不備があってもサービスを継続できる仕組み。ネットワークが存在することを前提としている限り、土管を広げることでしかサービスを広げられないわけで、それは結局は土管屋に過ぎないと思うのです。「自分の土管屋としての限界に真摯に向き合い、土管の有無に影響されないサービスの提供の仕方を考えることが脱土管屋に必要なこと」だと私は思います。
ドコモ山田社長が中期経営ビジョン解説
ネットワーク上に機能を埋め込んで行って端末をシンクライアント化していくというコンセプトを語り、これをもって「単なる土管化を防ぎたい」と言っているわけですが、私はこれは時期尚早、というか、それを前提としたサービスを基本に据えることは根本的に間違ってるだろ、と思わざるを得ません。言っちゃぁなんだけど、他のキャリアも含めて、「単なる土管」にさえなれてないよね、実際。地下鉄トンネル内は相変わらず圏外だし都市部では網の輻輳でパケットが通らなくなることなんて日常茶飯事。当然、エリア化されていない地域もまだまだ多く、ちょっとしたお出かけでも圏外に当たることはいくらでもあります。何より(高額な料金を払わない限り)海外は圏外だよね。ということを本当に自覚してないんですよ、この発言は。通信が電波や線に頼ったサービスである限り、それが届かない場所は必ず残るんです。どんなに頑張っても。なのに、「通信が疎通していることを前提としたサービスを基礎的サービスとして位置付けていく」というのは、おこがましいにもほどがある。不遜ともいう。ネットワークの提供は頑張るけど、それでも届かない人のためにもいろんな仕組みを用意してあげようというのが、土管化を防ぐために必要なことじゃないかなぁ、と思うんです。そのために、端末などのエンドノードにいろんな仕掛けをしてあげて(もちろん対向の提供側向けにも仕掛けは必要)、仮にネットワーク(=土管)に不備があってもサービスを継続できる仕組み。ネットワークが存在することを前提としている限り、土管を広げることでしかサービスを広げられないわけで、それは結局は土管屋に過ぎないと思うのです。「自分の土管屋としての限界に真摯に向き合い、土管の有無に影響されないサービスの提供の仕方を考えることが脱土管屋に必要なこと」だと私は思います。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds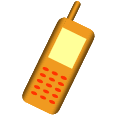 for Mobile
for Mobile
ウィルコムがダメになったのもそんな感じでしたね<社内の抵抗勢力