ウィルコムは既に破綻企業、実質ソフトバンクグループ入りした以上個別に扱うのもちょっと変かも知れませんが、しかし一応ほら、一発逆転があるかもしれないし。
ウィルコムは2004年の独立から2005年の音声定額でブレークしましたが、それ以外の時期は、いまひとつ存在感がありません。存在感が無いというか、存在していなくても世の中変わらないというか。唯一無二の価値を提供できていないという感があります。
たとえば2000年から2004年までのKDDI時代、データ通信を主軸にした展開を行いましたが、これもいかにも消去法的戦略。音声では見放されているし本体と競合するし仕方なくデータ専業に、と言う感じ。
そして、2006年にソフトバンクの音声定額が始まると、今度は自主的なサービス拡大を放棄し、「低電力高音質は唯一無二の価値である」と言って動きませんでした。ウィルコムのテーマは、「動かない」、これに尽きます。
業界では最も小さな身なりで一番動きやすい体質であったはずにも関わらず、わずかな減収のリスクが怖くて動けない。わずかでも品質が落ちるリスクがあると動けない。わずかでも失敗のリスクがあると動けない。ひたすら動かない会社。動いたのは、外から入った社長が指揮を執っていたわずか2年の間だけでした。今のウィルコムの収益源はその2年のわずかな成功にすべて依存しています。
そして、あらゆる施策がすべて「コスト削減」を志向しています。コスト削減とは「会社の縮小」です。自ら船底に穴を開けゆっくりと沈むという決断です。ITX投資はNTT依存からの脱却と言う前向きなコストだったはずなのに、ITXだからこそ実現できるサービスというのはついぞ現れませんでした。結局、「アクセスチャージ削減」と言う後ろ向きの目的が主になってしまっていたと考えられます。
大胆な値付けもできず大規模な販売や投資をするほどの資金も無く採用技術に圧倒的優位があるわけでもない。条件だけ並べれば、破綻すべくして破綻したということがよく分かります。今挙げたうちの一つでも解消できればまだ違った未来が見えます。そしてこの中で、ウィルコムと言う会社に実現できるのはただ一つ、「大胆な値付け」だけです。
消去法で経営するだけでも実は答えは簡単だったはずなんですね。不振になる前に、少なくとも私が別サイトで「音声定額はバブルだ」と指摘した頃に「大胆な値付け」を検討し、他社追随の機先を制して実施していれば、このような状況にまで落ちることは無かったでしょう。あのころ、ウィルコム社内にはバブルだという意識は無かったのでしょうか。
今後ウィルコムが立ち直るには何をするべきか。もう答えは一つしかなく、「大胆な値付け」です。とにかく、サービスプロバイダとして「動く」ことです。サービスの本質は値付けです。サービスを提供している会社として何か施策を打つのであれば、それはまず「値付け」からスタートしなければなりませんし、値付けを動かすことなく会社を動かす方法はありません。大胆な値付けは社員のモチベーションも高揚させるはずです。
破綻企業としてどうあるべきか、唯一のPHS事業者としてPHSと言うシステムの社会的責任をどのように総括するか、「潔く腹を切る」と言う選択肢もまたあるのかもしれませんが、もし「もうひとあがき」を考えているのであれば、今度こそ、サービスプロバイダとして「動く」こと、「値付けを動かす」ことを考えるべきでしょう。
 TWEET
TWEET
 Home
Home Feeds
Feeds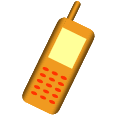 for Mobile
for Mobile
SBの子会社となり取締役も発表されましたけど、結局は破綻企業としてSBに利用されたのちにはPHSを完全に消す為に、送り込まれた役員さん達なんでしょうか。
破綻は終わり再盛発展していく事が、経営陣としての手腕を発揮できるとおもうのです。とは言いたいものの、所詮足掛けに使われ蹴落とす経営結果になると信じていたほうが、気が楽かもしれない。
NTTがやってきた事と同じ結果を繰り返すのもおもしろいのかもしれない。